

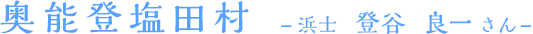
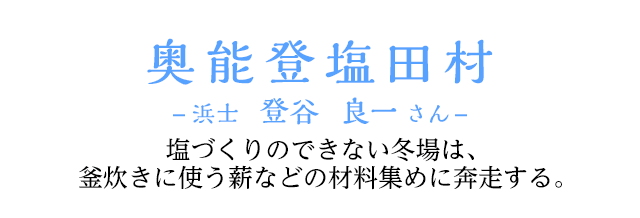
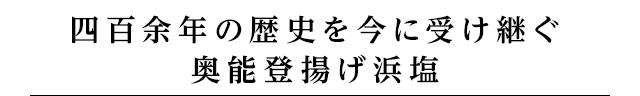

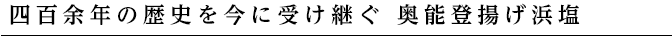

일본에서 가장 오래된 가집인 만요슈에는 ‘해조소금 굽기’라는 기록이 남아 있고, 그 당시에는 해조에 부착된 바닷물을 원료로 했습니다. 이후 염전을 사용한 제염법이 확립되어, 크게 ‘아게하마식’과 ‘이리하마식’이라는 2가지 제염법이 도입되었습니다. 큰 차이점은 바닷물을 퍼올리는 방식. 아게하마식은 사람의 힘으로 바닷물을 퍼올리고, 이리하마식은 조수 간만의 차를 이용하여 바닷물을 도입시킵니다. 염전에 뿌려 농축한 바닷물(함수라고 한다)을 가마에서 졸여 결정을 석출시키는 이 2가지 제염법은 오랜 시간 일본의 소금 생산을 담당했습니다.
메이지시대에 들어서 소금 전매제를 국가가 제정. 쇼와시대에 들어서는 완만한 경사지와 댓가지를 이용하여 함수를 만드는 ‘유하식(流下式) 염전’으로의 전환을 거쳐, 전기 에너지로 함수를 만드는 ‘이온교환막법’으로 바뀌었습니다. 다양한 발전을 이룬 제염 기술이지만, 1971년 염업 근대화 임시조치법의 제정으로 바닷물로부터 직접 소금을 얻을 수 없게 되었습니다. 이로 인해 약 2,000헥타르의 염전이 자취를 감추었지만, 문화재로서 유일하게 염전에서 제염을 계속해온 곳이 바로 노토의 아게하마식 염전입니다. 특색 있는 제염이 각지에서 활발해진 것은 사실 1989년 이후의 일입니다. 소금 전매제가 폐지되고 제염과 판매, 해외로부터의 수입이 모두 자유로워져 제염 업계는 급속히 확대되었습니다. 다양한 제염 기술을 도입하여 제염소마다 특색 있는 방법으로 소금을 만드는 와중에도 오랜 세월 변함없는 기법을 지켜온 오쿠노토 제염마을의 제염은 귀중한 가치를 지닙니다.


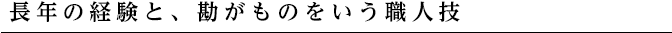
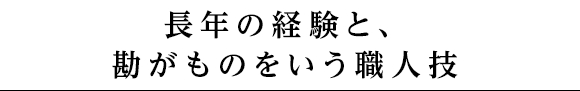

눈 앞에 펼쳐진 바다에 들어가 직접 바닷물을 퍼올리고 운반해 염전에 뿌리는 작업은 그야말로 중노동입니다. 퍼올린 바닷물은 호를 그리듯 안개처럼 골고루 염전에 뿌리는 것이 비법이라고 합니다. 제염업에 종사하는 사람을 노토에서는 병사라고 부르는데, 병사처럼 능숙하게 바닷물을 뿌릴 수 있게 되기까지는 아주 오랜 시간이 걸리는 만큼, 높은 기술력을 요하는 작업입니다. 작업이 한창인 여름에는 한 번에 1000리터나 되는 바닷물을 염전에 뿌려 천일(햇볕)의 힘만으로 염분 농도를 높입니다. 비가 내리면 작업을 할 수 없습니다. 작업을 할지 말지는 그날 구름의 움직임과 수평선 등을 보고 병사가 오랜 경험과 감으로 결정합니다. 햇볕의 힘으로 염분 농도를 높인 모래를 모아 바닷물로 걸러 함수를 만들고 이것을 가마에서 끓입니다. 장작으로 6시간 정도 끓이는 ‘아라타키’ 다음으로 드디어 시작되는 ‘혼타키’ 과정은 17~18시간이 걸리는 힘든 작업. ‘가마의 불조절로 소금 만들기가 결정된다’고 할 정도로 중요한 작업으로 잠시도 집중력을 잃어서는 안 됩니다. 여름철 가마가 있는 곳은 밤에도 60도를 넘습니다. 이곳에서 고된 작업이 이어집니다. 가장 어려운 것은 소금을 꺼내는 타이밍. 불 세기, 여열, 소금 모양의 변화... 아주 작은 판단 실수로도 소금에서 쓴맛이 난다고 합니다.
꺼낸 소금은 거출장이라고 불리는 소금을 건조하는 장소로 옮겨 약 3일간 방치하여 간수를 날립니다. 이로써 부드러운 소금이 완성됩니다. 에도시대부터 이어온 수고스러운 작업공정은 ‘手塩にかけて(‘손에 소금을 묻혀’라고 써 ‘몸소 돌보아 기른다’는 뜻의 관용 표현)’라는 말을 실감케 합니다.

